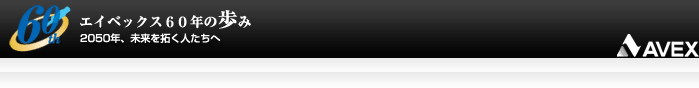
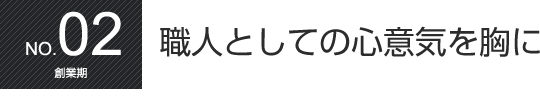
 当時の社風は、“職人が集う町工場”だった。創業者の丁稚奉公時代がそうだったように、いきなり現場に出され、先輩の仕事を見て覚える時代だった。「社員研修?そんな贅沢なもの、あるわけがない」と、当時の社員は一笑に付す。「誰も教えてくれず、厳しかった。でも、自分で覚えた仕事は、絶対に忘れません」と、誰もが言う。先輩も後輩に「きちんと(仕事を)見ろ、後は自分でやれ」と、背中で教えることに努めた。
当時の社風は、“職人が集う町工場”だった。創業者の丁稚奉公時代がそうだったように、いきなり現場に出され、先輩の仕事を見て覚える時代だった。「社員研修?そんな贅沢なもの、あるわけがない」と、当時の社員は一笑に付す。「誰も教えてくれず、厳しかった。でも、自分で覚えた仕事は、絶対に忘れません」と、誰もが言う。先輩も後輩に「きちんと(仕事を)見ろ、後は自分でやれ」と、背中で教えることに努めた。
その頃はまだ、工程設計という概念すらなかった。「社長が仕事を取ってきたら、完成図面を見て、自分たちで段取りを組みます。それぞれが、頭の中で考えてやっていましたよ」。それで仕事が進められる会社の規模だったとも言えるが、それ以上に各人の自主性と計画性が問われていたとも言える。
 今の時代では考えられないこともあった。邑松氏は「まず、材料からやっかいでした。仕入れた鉄材が、錆びていたり形がいびつだったり…」と言う。いわゆる「黒皮材」を、まず、一つひとつ自分で成型する必要があったのだ。「長さもバラバラなので、機械を横送りして長さを揃えていました」。もちろん今の材料なら、正確に形が整っているので、穴を開けて熱処理して研磨するだけでいい。
今の時代では考えられないこともあった。邑松氏は「まず、材料からやっかいでした。仕入れた鉄材が、錆びていたり形がいびつだったり…」と言う。いわゆる「黒皮材」を、まず、一つひとつ自分で成型する必要があったのだ。「長さもバラバラなので、機械を横送りして長さを揃えていました」。もちろん今の材料なら、正確に形が整っているので、穴を開けて熱処理して研磨するだけでいい。
とにかく、何もない時代だった。自分で道具を作ることから始める、職人的な気質から始めないといけなかった。「チップも、昔は自作する必要がありました。休みの日に出社して、作ったもんです」と、久野氏。ただし「自作だからこそ、高度な仕事ができる。そういう技術は失って欲しくないですね」とも。
例えば、針棒メタルなら100分の5ミリ程度の精度が要求される。「それもすべて、人の手で調整しました」。
邑松氏は「研磨の火花を見れば、どれだけ削れたかは、だいたい分かります。あの頃は、機械の未熟さを技術でカバーしていました。みんな職人の誇りがあった」と。
当時から「技術の加藤精機」と、定評があった加工技術。「目で見るだけで、ある程度の検査もできる。今の若い社員にも、そういう目を養ってほしいですね」と、加藤守氏も後進へのアドバイスを忘れない。
![]()